、
自宅のお隣の土地は半分に分割販売していましたが、ウチに近い方は売れたようで
基礎工事が始まっています
、

前回の解体工事もそうでしたが、真近に一から新築工事を見れるのはとても勉強になります
、
、

間口はウチより少し狭いですが、うまくレイアウトして駐車場のスペースも確保しています
それに比べると、ウチの門周りにはかなり無駄があるように思ったので、
隣の工事の音がある間に、ウチの外構もこの際やり直すことにしました


普段はデッキの下にヨメの軽を置いてるんですが、セレナがあるときは前に横向に置いてました
前の道は比較的広くて向かい側に家がないので、30年近くこれで問題はなかったんですが
一応路駐になるし車の出し入れも面倒なので、前から何とかしたいとは思ってたんです
、

間口が狭いわりに階段の横に広いデッドスペースがあるので、ここを使えば2台縦に並びそうです
、


今の階段はまだ新築の時に、二人で壁に足場板や床にタイルを貼ったりしてDIYしたのですが
これも大分傷んできてたので、ちょうどいいタイミングかもしれません(逆によくもってたもんです)
、
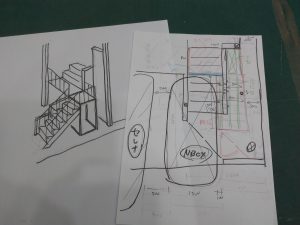
採寸してからプランを立ててみましたが、門と階段を4段分やり替えれば、何とかいけそうです
(少し前に飛び出すので、車庫証明は取れませんが)
ただそのためには、いろいろクリアしなければいけないことがあります
、


まず、撤去しなければいけない真ん中の門の壁の上に、ウッドデッキの柱が乗っています
ウッドデッキは残したかったので、この柱を切っても大丈夫なように補強することにしました
、
、


両面を防水塗装したコンパネで塞ぎました。枠だけでは弱いですが、面材を付けることで
一枚物になり、柱に替わる大きな棚受けができたことになります
雨が中に入らないように、上をルーフィングで塞ぎました
、


それでもこれだけではまだちょっと不安なので、家の柱に付ける金具を作って
そこからワイヤーで梁を吊りました
、

さらに階段ができたら梁も金具で繫いで、階段手摺りのポールで支える予定です
、
、


切った柱を抜くときはさすがにちょっとビビりましたが、特に垂れることもなかったので
後でデッキにも(恐る恐る)乗ってみると、全然びくともせずにがっちりしてました
まずは第一関門クリアです
、
 →
→ 
その壁の横にDIYで作った花壇と水栓スペースも撤去しましたが、この壁を取るのは一番最後の予定です
、


次はこの階段横の壁です
最初はこのままで、右側に新しい階段を付ける予定でしたが、それでは狭まかったので
この壁をまたぐ形に変更したために、上の当たる部分をカットしなければいけなくなりました
でもこれはコンクリートでできています
、

中がコンクリではなくブロックでできてることを期待して、サンダーの刃をコンクリ用に替えて
両面から少しずつカットしていきます
、


途中で刃を大きいものに替えてなるべく深く切ってから、バールを入れてまず上の段を取りました
中はやはりブロックだったので比較的楽に切れましたが、つなぎ目はセメントと鉄筋が
入ってるのでかなり苦労しました
、

次に下の段ですが、ここは新しく付ける階段に合わせて段々に切ります
、

一番下の段が、ブロックではなくコンクリだったので、持ってたハンマードリルで割りました
、

この壁の右側に新しい階段の受けを固定する予定です
エゴの木をなるべく切らずに残したいのですが、ギリギリです
、


新しい階段は鉄で作るんですが、それができるまで仮の階段を足場板で作りました
奥に入れる道幅も残したいのですが、この階段幅ではやはり狭いですね
、
並行して工場でその階段を作っていきます


本体は加工がしやすい30角のLアングルで作って、天板は人工樹脂のデッキ材を使います
、


階段の支えは、さっき言ったように最初は2本の予定だったのを、後で3本に増やしました
この1本目と2本目の間に、壊した壁が入るプランです
、
、

分解できるように全てボルト組なんですが、そのボルト穴を開けるのにこのドリル歯は便利です
サンダーの刃も今の物は薄くて切りやすいし、昔仕事で鉄工をやってた頃に比べるとホント進化してます
「あの時これらがあったら、ずっと楽だったのにー!」と、つい思ってしまいますね
、


その段々に踏板の天板の乗せると、ほぼ全体の形が見えてきました
後は手摺りを付けて天板を貼れば完成ですが、続きは来月です

























































































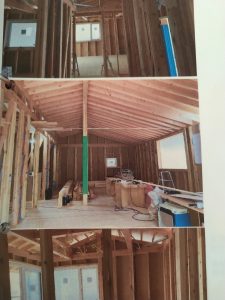

































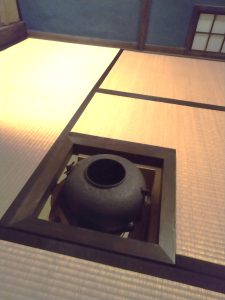














































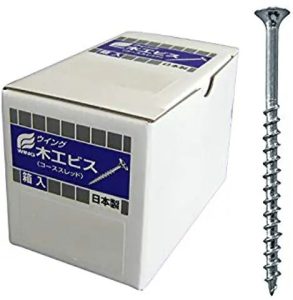


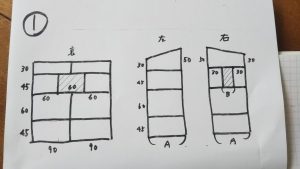
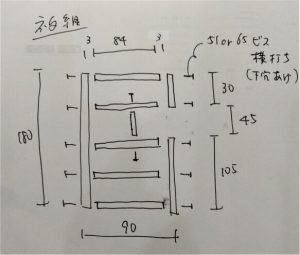

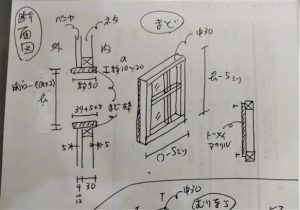
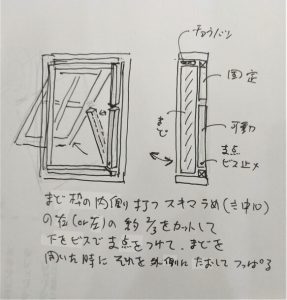





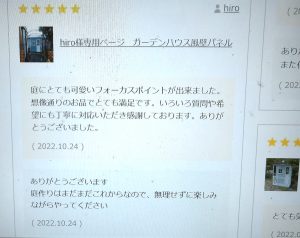







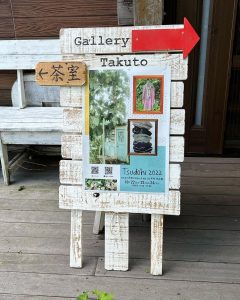

















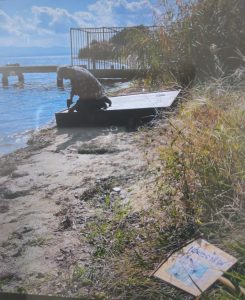
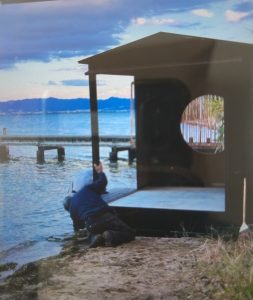










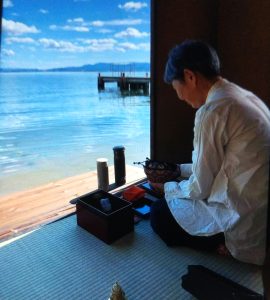















































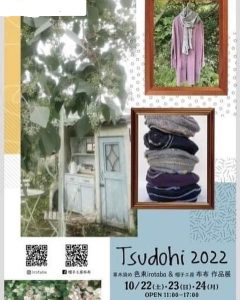
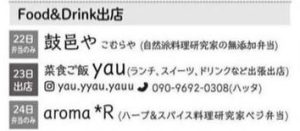












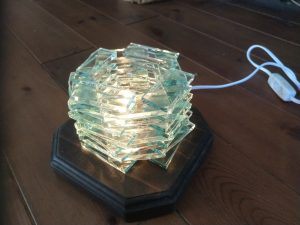











 →
→




 →
→ 






















































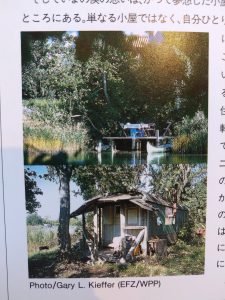
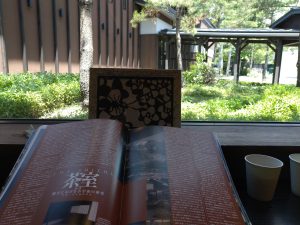























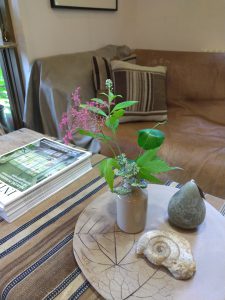


















 →
→ 














